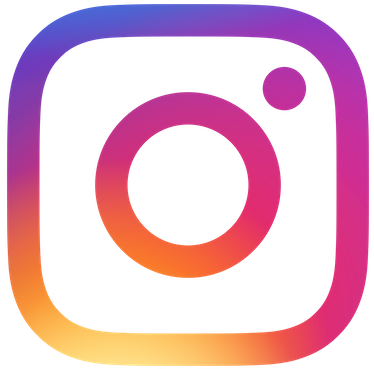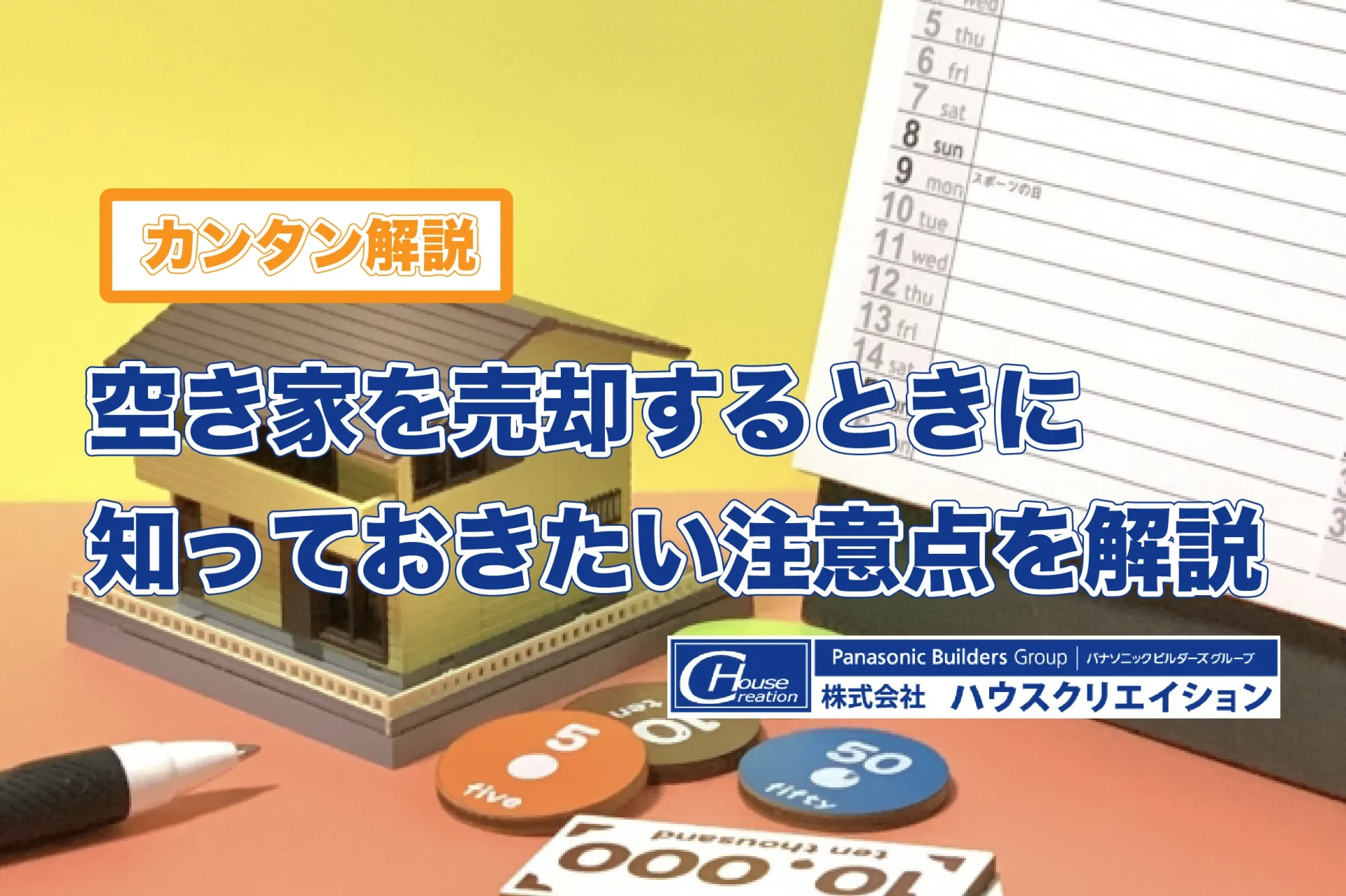リフォームと建て替えどちらがおすすめ?費用感・判断基準を紹介

家を建てて30〜50年経つなど、築年数が経過した家は「リフォーム(リノベーション)」するのがよいのか、「立て替える」のが良いのか迷っていませんか?
本記事では「リフォーム(リノベーション)」と「建て替え」の費用感を紹介しつつ、リフォーム(リノベーション)か、建て替えをするべきなのかの判断基準も紹介します。
実際の当社の施工事例も合わせて紹介していきますので、そちらも参考にしてください。
リフォームと建て替えの費用感
住宅を建て替えようとすると、一般的に1,500万円〜2,500万円ほどかかる場合が多いです。
対してリフォームの場合は、部分リフォームだと数十万円から300万円、全体リフォームを行なったとしても1,000万円未満で行えることもあります。
もちろん、どの程度リフォームを行うのか、どのランクの設備を入れるのかなどによって費用感は変わってきますが、建て替えより、リフォームの方が予算や費用は安く済ませれる場合が大半です。
以下から「リフォーム」「建て替え(新築・注文住宅)」の当社施工事例をご覧いただけます。
それぞれどのような仕上がりになるのか、ご参考にご覧ください。
>> リフォームの施工事例は こちら
>> 建て替え(新築・注文住宅)の施工事例は こちら
リフォームのメリット
建て替えとリフォームを検討した場合、リフォームには以下のようなメリットがあります。
- その①・・・費用が安い
- その②・・・工事期間が短い
- その③・・・住みながら改修できる場合も
順に解説していきます。
費用が安い| リフォームのメリット①
リフォームの場合、建て替えに比べて費用を安く抑えることができます。
予算が限られている場合は建て替えより、リフォームがおすすめです。
工事期間が短い| リフォームのメリット②
リフォームだと立て替えるよりも工事期間が短く済みます。
建て替えの場合は、既存住宅を解体するなど工数が多くなり、その分工事期間が長くなります。
早く改修を終わらせたい場合も、リフォームがよいでしょう。
住みながら改修できる場合も| リフォームのメリット③
リフォームの場合、改修箇所によっては住みながら改修することも出来ます。
建て替えだとどうしても一度仮住まいで暮らさなくてはならず、住み慣れた家を改装している間、離れなくてはいけません。
もちろん、リフォームの場合も工事範囲が広いと、既存住宅に住み続けることが難しく仮住まいで暮らさなくてはいけくなる場合があります。
建て替えのメリット
一方、建て替えには以下のようなメリットがあります。
- その①・・・間取りを一から決めることができる
- その②・・・耐震対策や断熱対策をしやすい
順に解説していきます。
間取りを一から決めることができる| 建て替えのメリット①
建て替えることにより、新築時同様間取りを一から決めることができます。
築年数が経ってしまった既存住宅が建てられた当時とは生活や家の在り方が変わっていることが多く、リフォームだけでは対応しきれないことがあります。
そのような場合は建て替えを検討するとよいでしょう。
耐震対策や断熱対策をしやすい| 建て替えのメリット②
耐震性の向上や断熱対策行いたい場合は建て替えがおすすめです。
1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認されている建物は「新耐震基準」と呼ばれる耐震基準をクリアしており、震度6,7の地震でも倒壊しないよう作られています。
1981年(昭和56年)5月31日以前に建築確認されている建物に関しては「旧耐震基準」という耐震基準をもとに建築されており、震度5強の地震に耐えられる、仮に破損があっても修復すれば建物が利用し続けられるという基準で作られています。
この「旧耐震基準」は1950年(昭和25年)に施行されており、1950年以前の建物の場合、耐震基準がなく、地震が起こった際に倒壊してしまう恐れがあります。
既存住宅の耐震基準を確認し、耐震性が不安である場合は建て替えを検討しましょう。
リフォームと建て替えの判断基準
「リフォーム」と「建て替え」どちらにするのか、それぞれの判断基準は以下を参考にしてください。
- 費用を抑えたい・予算が限られている
- 工期が短い方が良い
- 住みながら改装したい
- 改修したい箇所が部分的
- 間取りを1から決めたい
- 耐震性を高めたい
- 断熱性を高めたい
「リフォーム(リノベーション)」「建て替え」どちらもメリット・デメリットがあります。
当社の施工例もありますので、参考にご覧ください。
>> リフォームの施工事例は こちら
>> 建て替え(新築・注文住宅)の施工事例は こちら
当社では京都市内(山科区)を中心に注文住宅の設計・建築、リフォーム工事など行なっております。
「記事を読んだが、うちの場合どうすれば良いかわからない」
という方はお問い合わせいただけましたら、ご相談に乗らせていただきます。
お気軽にご相談ください。